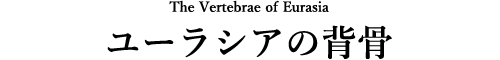大村湾は長崎県の中央部にぽっかりと空いた湖のような穏やかな内湾だ。
地の理に詳しくない人のために書いておくと、北部の湾口が非常に狭く極めて閉鎖性の高い海域のため、夏には赤潮や貧酸素水塊が頻発する。
そのような特性から一時期は海洋汚染の象徴ともいえる場所だったのかもしれない。
しかしエメラルドグリーンの艶麗な湾にはスナメリの群れが暮らし、何種類もの魚も息衝いている。
この湾の東岸に敷かれたローカル線がJR九州の大村線である。

その歴史は古くかつては帝国海軍所縁の路線であったが、日本一長い海岸線をもつ長崎の住民の生活の足として、いまでも立派にその役割を果たしているようだ。
列車はリアス式の海岸線に沿って幾重にもカーブを描きながら走行する。
学生の時分には長崎空港に着陸する機窓からいつも目にした大村湾も、列車の窓から眺めるのはこの時がはじめてだった。
いつからだろう。
最近はすっかり航空機に嫌気がさして列車の旅に強く憧れるようになった。
海沿いの駅は全国にいくつもあれど、千綿駅ほど素朴で美しくどこか郷愁を誘う場所は数少ないであろう。

首都圏にも海芝浦という臨海の駅があるが、こちらは某企業の工場のために造られた無味な工業地帯の駅である。
いつか行こうと思いつつもその機を逃すということが、人生では往々にしてある。
あの風景が残されているうちに記憶に焼き付けておかねばならないと、彼の駅を訪れたのは昨年のことだ。
この駅がある東彼杵郡は、きっと一見では何と読めばよいのか分からない長崎の難読地名の部類に入るだろう。
長崎に引っ越したばかりの私は「ひがしかます」なんて見当違いな読み方をしていた。
いやいや、魳じゃないんだから。

千綿駅は山と海に囲まれた木造駅舎にコバルトブルーのディーゼル気動車がやってくるという、旧国鉄の趣が色濃く残る風光明媚な駅だった。
私は古くて趣のあるものをとにかく愛している。
青春18きっぷの宣伝ポスターに使われたこともあるプラットフォームが、いまも静かにそこに佇んでいた。
古びた駅舎の前にある同じように古びて色褪せた赤い郵便ポストは、さながらその場に華を添えているかのようだ。

ちなみに駅舎には千綿食堂というスパイスカレーを提供する店が入っており、メニューが日替わりカレーのみの頑なで一途な姿勢を貫いている。
もっとも店を営んでいるのは頑固親父とは対照的な、今風の若い(とはいっても私よりは歳上の)ご夫婦なのだが。
注文を済ませて待合室のテーブルに掛けていると、地元住民が列車ではなく自家用車に乗って続々とやってきた。
大変人気で毎日売切れ御免だというスパイスカレーを堪能しつつ、木製引き戸の窓枠越しに海を目をやってみる。
波は今日も穏やかで曇天の下でも明るく鮮やかなブルーを湛えていた。

近頃はIC改札機が普及して久しいが、未だほとんどで導入されていない大村線では列車に乗るために切符を購入する機会がある。
もっともローカル線は大概乗車時に整理券を受け取り、下車する際に運転室の後ろにある運賃箱で切符か現金で精算するという路線バスのような形式をとっているため、事前に買わずとも何も問題はない。

ただし列車はワンマン運転なので、無賃乗車をさせないために無人駅などではドアの開かない車両があるのだから困りものだ。
田舎のローカル線にはじめて乗った時には、降りたい駅で乗っている車両のドアが開かず驚いた経験がある人もいることかと思う。
かくいう私も、千綿駅のホームから乗ろうとした位置のドアが開かなかった一人である。
さて。
千綿駅で切符を買うことに話を戻そう。
ここで切符を購入すると他とは変わったちょっと面白い体験ができる。
簡易委託駅といってJRの職員が常駐しないこの駅では、手売りの常備券や軟券乗車券という類の切符を買うのだ。

それだけでは他の簡易委託駅と何ら変わりはないが、勘の良い諸氏はその委託先にお気づきのことと思う。
ご存知、千綿食堂なのである。
カレー屋から列車の切符を買う経験は人生でもそう多くはないはずだ。
ちょうど厨房が昔の駅務室跡に位置するらしく、その片隅に残されたかつての改札窓口でカレーの盛りつけをしていた奥さんが、その片手間に早岐駅までの切符を売ってくれた。
鉄道旅行の途中下車でこれほど魅力的な駅はおそらく滅多にないだろう。
だが、この路線の代名詞的存在であったキハ66・67系気動車は、二〇二一年六月もって姿を消したという。
国鉄分社化後の困難を生き抜き、JR九州の株式上場まで見届けてきた古兵も、夏草をさざめかした後の風のように過去のものへと成り果てたのだ。
しかも新しく導入された新型の車輌は、デコトラとも烏賊釣り漁船ともつかない妙な電飾を備えたちんちくりんな風貌。
またひとつ古き良き時代の名残が失われたのだろうか。

「良いものでいいものは守り抜く。新しいものは絶え間なしに勉強してるけど守り抜く。その気迫と気概があります。立派だと私は思いますね。こういう精神の伝統が欲しい。」
かつてロンドンを訪れた開高健はそんな意味合いのことを語っていた。
市内を走るBlack Cabの意匠や、現代建築に押し挟まれて建つウナギの寝床のようなTWININGの本店。
そこに西の変態島国と揶揄される英国に於ける、保守の鑑をみたように思う。
老兵の走り去った駅は何かが微妙に、しかし決定的に違ってしまっているかのようだ。
あの日、駅舎を出ると単線の軌道を挟んですぐ目の前が海であったため、思わず釣りをしてみたくなる衝動が湧いたのを憶えている。
勿論、駅構内での釣りなど列車の往来には危険極まりない行為であり実際には不可能なわけであるが、それは釣師の性というものだろう。
なかなか来ない帰りの列車を待ちながら、誰もいない駅のホームでひとり眼前の海に糸を垂れて空想に耽る。
もしもあの駅でそんなことができたのなら、きっと乙なものだったんじゃないだろうか。
鮮やかなコバルトブルーの列車がいまも記憶に鮮烈な印象を残して離れない。