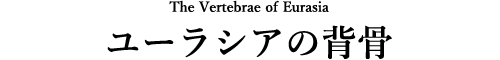鳴く虫の趨勢が、セミたちから秋の虫へと移ろいつつある季節の短い狭間、僕は都内にある小さなバルコニーにいた。
ここは、Fさんがその人生の多くを過ごしてきた、自宅マンションの一角だ。観葉植物に囲まれ、片隅には見事な木彫りのブラックバスが鎮座している。
サイドテーブルに置かれた小箱から、煙草を一本取り出して火をつけると、フォールディングチェアに深く腰掛けたFさんは、紺色の夜空を目がけて、そこに漂う雲と同じ色の煙を吐きかける。
眼下の首都高速を駆け抜ける車と、一定の周期で点滅する高層ビルの呼吸。
いつもと変わらない光景。
Fさんとの友人関係が始まって以来、僕たちはこの場所で何度も語り合った。
時には他の仲間を交えて。そして時には、今日のように僕たち二人で。

かつて文字通り世界中を渡り歩いたという、現役時代の釣りの体験談は、アラスカのキングサーモンを筆頭に、オーストラリアのロウニンアジからコスタリカのターポンまで、多岐にわたる。
それは、さながら子供の頃に読んだ冒険小説のように、雄大で鮮烈で面白かった。
それもそうだろう。僕らは倍以上も歳が違うのだから。
一般論からすれば、それはただの我儘だろう、とさえ思える、独自の矜持が飛び出したことも、一度や二度では済まない。
彼の口から語られる、決して絢爛豪華ではなくとも、豪快で満たされた人生の話。
無論、辛い経験も数え切れないほどあったろうが、こんなにも豊かな人生を送っている人間は、少なくとも僕の知る限りは他に存在しない。
それが僕には羨ましくてたまらなかった。
だから、この場所に来ると、いつも人生について考えてしまう。
そうだ、ここを「人生の庭」と呼ぶことにしよう。さっき、勝手にそう決めた。
*
夏の終わり。三十年ぶりに東京へ来ることになったNさんを、Fさんと僕ら親子の三人で、我が家の山の別荘へ迎えることになった。
もはや見慣れて何の感慨も感じなくなった空港の到着出口で、東京へと降り立つ彼を待つ。
「そういえば、サプライズ好きのNさんのことだから、こっそり後ろに立っていたりしてな。」
そう思って、何の気なしに振り返ると、背後にNさんが立っていた。本当にいた。別に驚きはしなかったし、ああやっぱりか、といった思いだったが、僕の率直な感想は、「してやられた。」だ。
しかし、羽田空港が想定外の駐車場の混雑に見舞われたこの日、Nさんは東京に着いて空港から出ることもなく、飯にもありつけずにFさんの車に乗り込まされると、訳の分からない複雑怪奇な高速道路のインターチェンジへと直行させられたのだ。こちらは、Nさんにとっても、想定外のサプライズだったことだろう。
我が家の別荘に着くと、父は賓客をもてなすべく、既に手料理の支度を整えて待っていた。
Nさんは少し恐縮していたかもしれないが、当の本人である父は、実に嬉々として、気楽そうにやっていたものだ。今年の春、朱鞠内湖でMさんやその友人のSさんに見せていた態度とは大違いだったから、まず間違いない。

その理由は、過去に紋別や阿寒で会って釣りをして、気心が知れていたNさんが相手だというのもあるだろう。
だが、それ以上に父からすれば、Nさんとの間に何かしら相通じるものを感じていたのかもしれない。
だからきっと、今度は自分の趣味で恩返しをしたかったのだ。
うちの父親にとって、別荘で客人を迎えるということは、釣り仲間のためにテントを張ってくれることと似ている。
だからNさん、どうか気にしないでください。
その日の夜、酒を飲みながら、Nさんと明け方まで話した。そういえば、Nさんと出会って以来、こうして腰を据えてじっくりと話をするのは、これがはじめてだったかもしれない。
“Helpless”
こればかりは、実際に経験した者だけが語れる生々しさに溢れている。
もちろん、彼と話したのは陰鬱なことだけではない。僕らが知り合って、一緒に釣りをするようになってからのこと。
最初に会ったとき、僕が釣りを放り出して、シラカバの陰で寒さと強風に震えていたことは、今でもときどき笑い話になる。
「前に97センチを釣っているだろう。今度釣れたのが70センチだったら、どう思う?」
「70センチでも、僕は釣れたら嬉しいですよ。」
「二匹目と三匹目も70センチだったら、一匹目と同じように喜べるかい?」
「きっと、一匹目ほどは嬉しくないでしょうね。」
「そうだろう。自分の中で、ある種の基準みたいなものができちゃうんだよ。だから、本当は、いきなりデカいのを釣って欲しくなかったんだ。」
そして、Nさんはこう続けた。「たいして感動もしないのに、無意味に魚に触れて傷付けるくらいなら、いっそバラしちゃったほうがいいのかもしれないな。」

Fさんは早々に眠りに落ち、二階からは時折、父のいびきが響いてくる。それ以外は、何の音もない、静謐なる山の夜。
煙草を吸いに外のデッキへ出ると、都会では姿の見えない星々が夜空に散らばっていた。Nさんは、火種の絶えたファイヤーピットに灰を落としている。
やがて、キッチンのテーブルに横並びで掛け直すと、Nさんは再び語りはじめた。経験を積んだ釣り人は、いくつかの段階を経て、やがては釣りそのものを止めてしまうというものだ。
「俺は自分よりも、一緒に釣りをする人が釣ってくれたほうが、ずっと嬉しい。逆に自分が魚を釣ることへの熱意は、だんだん薄れてくる。そのうち、もういいやって思い始めちゃうね。Mさんも、たぶんその域に達していると思う。長く釣りを続けていると、そうゆうふうになるんだよ。」
そうだとすると、イトウ釣りの名手であるMさんが、今年は持参した椅子に座ってばかりだったのも頷ける。Mさんが最も興奮していたのは、目の前で僕がサクラマスを釣った時だった。
それならば、釣りを休んで椅子に座り始めることも、釣り人が極致へと至るために経る過程のひとつなのだろうか。

「だから、春にMOさんがはじめてイトウを釣ったのもそうだけど、Yが釣らせてあげたってことがそれ以上に嬉しかったんだ。いまはまだ分からないだろうけど、10年後か20年後かには、きっと分かるようになる。」
夜も更けて午前4時を過ぎた頃、ようやく僕らは眠りにつくことにしたのだった。
最後の缶ビールを開けたとき、紋別の千里眼はこう呟いた。
「Yが同じ職場とかにいたら、きっと話が合わなかったと思う。」
僕も同感である。
考えてみればみるほど、奇特な関係だ。
職業も住む場所も共通点がなく、年に何度も会っているわけでもない(唯一、同じ都内に住む僕は、定期的にFさんご夫妻にお世話になっている)。
年齢だって上は70代から下は30代まで、最大で45歳も離れているのだから。
そんな人々が、イトウ釣りを通してつながっている。
そして、毎年釣りの時期になれば、自然と皆が予定を合わせて集まってくるのだから面白い。
友人や釣り仲間のようなものではあるのだが、実際のところそれが適切な表現といえるのか、僕ら自身もよく分からない。
僕が思うには、「同盟」と呼ぶのが相応しいんじゃないか、ということだ。
試しに、同盟について辞書を引いてみよう。
“国家・団体・個人などが同じ目的のために同じ行動をとるように約束すること。その約束によって生じた関係。”(Oxford Languages)

「釣り同盟」なんて言ったら、なんだかカッコいい響きじゃないか。それに、盟主という位置づけを、Fさんは気に入ってくれるに違いない。
ただ、ひとつ言えるのは、Fさんがいなければ、我々は釣り場で顔を合わせたとしても、決して今のような関係にはならなかったということだ。それぞれの人生が、奇跡のようなめぐりあわせを経て、いまの我々がある。だから、この不思議な縁が続くかぎりは、盟友たちと共に、釣りという人生の妙味を楽しみ、そして語り合いたい。
帰京して、いまは都心へ出かけているNさんの帰りを待たずに、人生の庭を後にしながら、そう考えた。
イトウ釣りを始めたことで、僕の人生は間違いなく変わった。それは自然の中で魚を釣る楽しみを知ったということもあるが、その過程で知り合った人たちによる影響のほうが遥かに大きいと思う。
Fさんから誘われ、Nさんに教わり、MさんやMOさんが一緒に喜んでくれなかったら、出汁醤油の中で出涸らしになった鰹節のように、僕の人生はきっと無味乾燥で、もっと退屈なものだったであろう。
だから、また来年も、春の溶けだす朱鞠内で会いましょう。