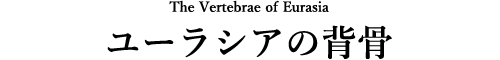いつかやろう。いつか行こう。
いつかが永遠にならないうちに。
そうして、それが永遠に叶わなくなるのは別に珍しいことでもない。
人生の予期しないタイミングで無常にも突如として眼前の機会は掌から滑り落ちてゆく。
僕もまた最近、ひとつの「いつか」を永遠へと変貌させてしまったひとりだ。
決して人生の大きな損失ではない。
しかし拭いきれない微かな後悔を葬るため。
そして、もうひとつのいつかを永遠へと変えないために。
令和四年の十月十三日、ようやく重い腰をあげた僕は旅に出た。
*
北海道第二の都市の中心駅を出ると軌道は大きく弧を描き、宗谷本線は一路北を目指す。
旭川の市街地を抜ければほどなくして人家は疎らとなり、列車は唸りをあげて国境にある峠の急勾配を越えてゆく。
やがて耕作地のなかに再び人間の営みが認められるようになると、和寒、剣淵、士別といったいくつかの街を経て道北の名寄へと到着した。
まだ路線全長の半分にも満たないが、この先から稚内に至るまでのあいだはその大部分がまともな都市の存在しない人口希薄地帯だ。
途中いくつかの小規模な町と集落が点在する程度で、人の住まわない原野や湿原や林が延々と続いている。
かつての繁栄の面影を残した長大な駅のプラットホームに降り立てば、いまや列をなさなくなった年季の入った気動車が寂しげにぽつんと佇むのみだ。

帰路につく途中、乗り換え列車の出発を待っていると、ふいにディーゼルの音を響かせながら反対側のホームへ本物の「列車」が滑り込んできた。
都会ではどうであれ、この地で四両編成というのはひどくに立派に見える。
鈍い銀色に輝くステンレス製で寒冷地らしさにあふれるこの車輌が僕は好きだ。
いくばくかの乗客がホームに吐き出すと、入れ替わりに同じくらいの客が車内へと乗り込んでゆく。
列ができていた場所はきっと自由席だったのだろう。
この先に広がる原野の名を冠した特急サロベツは、まるで路線の将来に立ち込める暗鬱を払拭したいかのように力強く最北の地へ向けて走り去っていった。
名寄から山を隔ててほど遠くない場所には幻の魚イトウが棲む朱鞠内湖がある。
湖畔のロッジから臨む山の反対側で、名寄の街の灯りが夜空を明るく照らすのが見えるほどの距離なのだ。
僕が生まれる以前には国鉄がここから朱鞠内の湖畔まで鉄路を敷いていたというのだから驚くかぎりだ。

名寄盆地にもいくつかの河川が流れているが、西麓の嶺によって朱鞠内とは水系を異にするらしい。
名寄川は天塩川水系、朱鞠内湖は石狩川水系だという。
この二つの水系を分ける分水界が塩狩峠をはじめとした名寄盆地周縁の山々いうわけだ。
隔離されたどちらの水系でも、イトウは現在も比較的安定して生き残っている。
しかし北海道に広く繁栄した魚族の帝王も、いまや緩やかに終焉への道を辿りつつあるのかもしれない。
その遺された数少ない小王国。
分水嶺を越えることのできない彼らは、別水系の同族と邂逅することもないのだろう。
これほど近い距離で同じ種族の全く違う一族が交わらずに暮らしているというのも考えてみると面白い。
地理的隔離が独自性を育む。かつては人間もそうであった。いまではすっかりそんなことは忘れてしまっているようだが。
それをみてイトウたちは何を思うのであろうか。
さて、再び北への遡上を続けるとしよう。
「車内の温度は暑くないですかね。」
かつては駅だった豊清水の信号場で上り列車との交換を待つあいだデッキにある便所へ立つと、同年齢くらいの若い運転士が親切に声をかけてくれた。

この辺りに多く出没する妖怪「レール舐め」を威嚇して汽車は事あるたびに「ピィー」とも「ピョー」ともつかない独特の警笛をけたたましく鳴らして進んでゆく。
妖怪レール舐め、つまり鉄分摂取のためレールを舐めにくるというエゾシカなのだが、彼らときたらやたら人馴れしていて列車が近づいてもなかなか逃げようとせず、むしろこちらをじっと見つめたり揶揄うように小走りで前を駆けていく始末なのだから手に負えない。
そんなわけで北の大地のローカル線は遅延させられることがしばしばだ。
北海道で最も人口の少ない音威子府まではそんな急ブレーキを途中幾度か挟みつつ、蛇行する天塩川に沿って揺られること一時間あまり。
この地も昔は木材の運び出しや鉄道の分岐点として栄えたという。
北地の小さな村には不釣り合いに大きなホームや構内の線路跡が、かつて長大な貨車を引いた蒸気機関車が行き交った時代の名残りを物語っている。

この地を知ったのは何度目かのイトウ釣りで朱鞠内へ向かう際にカーナビから流れた「音威子府方面」という音声案内がきっかけだったと思う。
その独特の響きと魅力的な字面に強く惹かれた。
いつか訪れたい。そして名産品であるという真っ黒な蕎麦を食べてみたい。
音威子府駅にある日本一と言われる駅そば屋でそれを食べられたらと思っていた。
それにせっかく駅そばを食べるならば、やはりJRの列車で行かねばなるまい。
それが僕自身の妙なこだわりでもあった。
だが道北は遠い。あまりにも遠かった。
四時間の滞在の対価として移動時間はその三倍だ。それも旭川に前泊をしたうえで特急列車を使って、である。
そうして訪問を後回しにしているうちに遂にその時がやってきた。
主人を亡くした駅そば屋が昨年閉店し、村内で唯一の音威子府そばの製造元であった畠山製麺も経営者の高齢を理由に今夏で廃業した。

職人としての誇りだろうか、味が変わることを嫌って事業を他人に譲ることはしなかったのだという。
こうして音威子府そばは夢幻の如く永遠に地上から消えてしまった。
唯一無二の特産品を失った小さな村はこの先どうなるのだろうか。
ひとまずこの駅は後にしよう。帰りの列車にはここから乗るつもりだ。
音威子府の隣駅、同じ村内にある筬島が今回の僕の下車地である。
人口は僅かに六世帯十人前後の集落で降りる客がいることが意外だったのだろう。
しかも他の乗客たちが利用しているフリーパスではなく僕は正規運賃の切符を買っている。
不思議そうな顔をして切符を受け取る運転士から乗車の礼を受けた。
もっともこんな小さな集落の駅で入れ違いに女性が一人乗車したことには、僕のほうがむしろ驚かされてしまった。
なにしろ名寄を発って以来、誰ひとりとして乗降する者はなかったのだから。

北海道ではよく見かける国鉄時代の古い貨車を改造した駅舎を覗いてから、いよいよ筬島集落へと足を踏み入れる。
現在の時刻は午前九時十六分。いま少し時間がある。
北地のこんな小さな集落を訪れた理由は、この地で創作活動をおこなった芸術家の彫刻をこの目で見るためだ。
筬島はいまでこそすっかり寂れているものの、木材の貨物出荷で栄えた最盛期の人口は六百人を数え集落には小学校があった。
駅前の廃屋の傍らにいまでも校門跡の柱があり、音威子府村立筬島小学校の銘が残されている。

校門横の廃屋は宿直の寝泊まりする小屋だったのだろうか。
この廃校舎をアトリエとして移り住んだアイヌの芸術家が砂澤ビッキである。
ビッキ亡き後の現在では「エコミュージアムおさしまセンター」と称して村の小さな美術館のような役割を与えられているようだ。
この元アトリエだが、冬になると翌年の春まで閉館してしまう。
雪深い時期にこんな僻地を訪れる物好きが多くいるはずもなく、来るかもわからない来館者のための除雪をするのは手間に見合わないのかもしれない。
つまり今年のうちに訪れるには、今月が最後の機会だったというわけだ。

学芸員の勉強をするためにこれまで多くの博物館や美術館を訪問したが、資金力の乏しい地方施設では管理の行き届いていない残念な展示を何度も見せられてきた。
ここの展示はどんな状態であろうか。
しかし、それはすぐに杞憂であることがわかった。
朽ちて土へ還ってゆく途中の巨大なオトイネップタワーの残骸。
かつては音威子府駅前に立っていたトーテムポールであったというそれは、屋内であるものの床板を取り外した土間のような空間で地面に晒されている。
資料の保存という博物館の役割とは、一見相反しているように思えるがしかし..。
なるほど壁に掲げられたキャプションに目をやるとその理由に納得させられた。
生きていくものが衰退し、崩壊していくのは至極当然であるというビッキの言葉を具現化した見事な展示方法なのである。

そして最後に待ち受けていた展示に圧倒されることになる。
「こちらからお入りください」
白い壁の案内にはそう一言だけ記されていた。
入口から中を覗けば、蝋燭ほどの小さな丸い灯りが数メートル先で足元の暗闇を心許なく照らしている。
ここは何の部屋なのだろうか。不思議に思いつつも小さな照明を通過したときだった。
狭く暗い通路で漆黒の壁に囲まれ灯りを背にしたことで、一瞬完全なる闇に囚われた。
この感覚、以前どこかで。
そうだ。学生時代に訪れた西表島だ。
研究室の仲間と夜の林道で懐中電灯一斉に消したとき。あのときもこんな感覚だった。
進むべきか戻るべきか。一瞬戸惑ったが慎重に右のつま先で前方を探りつつ一歩踏み出すと、左手に薄明りを感じた。どうやらここで壁が途切れているらしい。
反時計回りに振り向くと同時に、開けた空間と照明を浴びて佇む彫像が視界に飛び込んでくる。
それは歪んだ十字型の木像だった。
何千回と鑿で穿たれた跡がまるで魚の鱗や爬虫類の波打つ皮膚のようにもみえる。
先ほどの暗闇で一瞬とはいえ方向感覚を奪われたからだろうか。ゆらゆらと左右にゆっくり揺れながら、それが軽く会釈をしたかのような錯覚に陥った。
感動とともに全身に鳥肌が立っていくのが分かる。この部屋と作品には間違いなく樹氣が息づいているのだ。
音威子府そばの後悔とは別の形で、「いつか」が自分のなかで記憶となり永遠に変わってゆく瞬間。
ここに来られて本当によかった。
だってこんな素晴らしい作品に出逢えたのだから。
釣りにしたって同じことがいえるのかもしれない。
いつか実現したいと思っていたグレイシャーキングと呼ばれるサケの王様を釣る夢。遠きパタゴニアはいまや遥か絶域の彼方に感じられる。
こうして振り返れば会社の業績がまだ好調だった頃が最後の好機であったように思える。
多少の無理をしてでも地球の裏側まで遠征するべきだったのだ。

限られた場所とはいえ今はまだ決して幻の魚ではないイトウも、そのうち徹底的に保護されるか絶滅するかして釣ることができなくなる可能性だってある。
環境の変化や気候変動といった要因も冷水を好む鱒族には向かい風だ。
実際のところ最北の聖地にして最後の楽園ともいえる猿払川では、近年夏の渇水でイトウが大量死して数を減らしているらしい。
地元では自粛という体裁で禁漁期を設けているくらいだから、よそ者がのこのこと出かけて行って場を荒らすわけにもいかないだろう。
だから釣りに行く意志と能力のある人は、どうかその機会を逃して後悔することのないようにしてもらいたい。
帰りの列車に乗るため訪れた音威子府駅に常盤軒の暖簾はすでになく、無機質に閉ざされたシャッターには閉店を告げる簡素な貼り紙が残るのみであった。
蕎麦の実の甘皮をそのままに挽いたという黒く香り高い音威子府そばは、いったいどんな味がしたのだろうか。