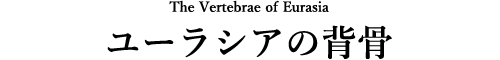壁に掛けた外気温計が未だ氷点下を示す冬の夜明け。
階下に置かれた薪ストーブからは、昨夜残した熾火が今なお微かな温みを放射し続けている。
窓の外ではアカマツの枝に霧氷が霧の花となって咲き、稜線から顔を覗かせた日の光を受けて光り輝きはじめた。
夜の間に付近を徘徊していたのだろう。
小屋の周辺にはシカや小動物らしき、夜の来訪者たちの足跡がそこかしこに残されている。
冷たい朝の風が一瞬、頬をなでると枯葉の残った枝を微かに揺らして去ってゆく。
静寂が訪れた。
いつもと違いハンドドリップのコーヒーで贅沢なカフェオレを作りデッキへ出ると、刺すように冷たい空気に包まれる。
熱い飲み物をひと口啜ってから、胸ポケットから取り出した煙草に火をつけてゆっくりと紫煙をくゆらせた。
誰にも入り込めない至高の孤独。
北海道でトラウトフィッシングをしている釣師のなかには、心のどこかにそんなものを抱えた人が案外多いのではなかろうか。
誰に語りかける言葉でもなく代わりに煙を吐き出しながら、ふとそんなことを考えていた。
孤独こそが最高の癒しとなる。
そんな時があったって良いじゃないか。
君もそうは思わないかい。
欧米ではキリストの生誕を祝う祭の習慣が、新しいもの好きで何でも貪欲に取り込む極東の島国に入ってきて百余年。
明治の世の人々も当初は「三太九郎とは何者でせうか?」などと不思議がっていたらしい。
それがいつの間にか企業の商戦に利用されるようになり、いまではこの国でこの日を喜ぶのは子供か付き合いだしたばかりのカップルくらいで、本来の趣旨に大きく反してすっかり聖夜ではなく性夜の様相を呈するようになったとみえる。
先日仕事で出会った金髪長身の紳士アンドレアスは今宵、ベルリンの自宅にて家族でクリスマスの食卓を囲んでキリストの生誕を祝うのだろうか。

そんな十ニ月二十四日に、単身信州の山に籠る男が一人。
師走生まれの悲しい性を抱えたのは、何を隠そうこの私である。
思い返せば幼少期より誕生日とクリスマスのプレゼントは毎年ひとまとめにされ、父親は大抵海外出張で家にいないなど、あまり良い思い出がない。
おまけに大人になってからは、ある年にスーパーの冷凍食品売り場で突然発症した末端冷え性に悩まされるようになり、体調が優れなければ精神衛生上ますますよろしくないとくる。
そして今年もまたひとつ歳をとった。
人は三十にして立つというが、今の僕は十年前の自分からおそらくまるで成長していない。
それはまるで、アクリル画に描かれたような薄い藍色に染まる十二月の憂鬱だった。
そんなものを抱えて過ごしていると、堪らなく何処か静かな場所で独りになりたくなるものだ。
「December blue」
この症候群を僕はそう名付け、毎年重軽の差はあれど向き合うことにしている。
数年前に父親が建てた我が家の山小屋は、そのような趣向におあつらえ向きの場所だった。
燃え続ける薪の炎は、この世で僕がいつまでも見ていられるもののひとつだ。
深夜に薪ストーブの耐熱ガラス越しにゆらめく炎を眺めていると、不思議と心が落ち着く。

昨夜はダッチオーブンを引っ張り出してチキンを焼き、安物のスパークリングワインでひとり乾杯をした。
自分の手で作った旨いものを腹いっぱい食べ、好きな音楽をかけながらしこたま酒を飲んで、酔い覚ましのコーヒーを手に一服してから眠りにつく。
そんな贅沢な休日。
朱鞠内のレークハウスで供されるような芸術的な焼き目を再現したくて、溶かしたバターや卵黄を塗ってみたりしてこれまでに何度も挑戦しているが、これが簡単そうでいてなかなか上手くいかない。

父が冷蔵庫に残してくれていた自家製ベーコンで、クリームパスタも堪能させてもらった。
彼が趣味で作るベーコンは、焼いて食べるには些か塩辛すぎると不評だったのだが、パスタに入れると凝縮されたスモークチップの香りと塩分を存分に発揮することを僕が発見して以来、一躍我が家で人気を博している。
若い頃からアウトドア全般、特に山遊びを好み、念願の別荘を手にした今も、相変わらず彼の仕事は多忙を極めるようだ。
それでも週末には足しげく通いつめて、豚バラ肉でベーコンを燻し、畑で野菜を育て、白菜や沢庵を漬けることに余念がない。
しかし、思い返してみればばもう何年も一緒に釣りにも行っていない。
ここでの週末を終えて、ひと足先に都会へ戻った父親のことを考えながら、彼が日々の煩わしさから解放され、本当の自由を手に入れる日が一日でも早く訪れることを切に願った。
凍れる寒さに思わずぶるりと肩を一度震わせると、僕は煙草の火を消して部屋の中へ戻ることに決めた。

ストーブの熾火は心なしか先刻よりも放つ熱を失いつつあるようで、室内には入り込んだ冷えた外気と静寂だけが残っている。
つかの間ソファに体を預け、無心で虚空を見つめていると急に実感がわいてきた。
精神の休暇は今日で終わりなのだ。
決然と立ち上がった先の視界に、薄青い十二月の靄はもうかかっていなかった。
さあ、東京へ帰ろう。
古びた軽自動車の運転席に乗り込むと、差し込んだキーを力強く回した。