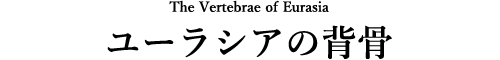心地よく晴れた11月のある日曜日の昼下がり。
かねてから訪れたかった茅ヶ崎にある開高健記念館を見学してきた。
芥川賞作家の開高健が晩年を過ごした旧邸宅を改装し、書斎や関連資料を保存する記念館として一般公開をしている場所だ。
人間というのは何とも単純なもので、「良い休日をお過ごしください」などと言われてしまうと、せっかくの休みを有意義に過ごさねばならないと、ある種の強迫観念のようなものが湧いてくる。
そんなわけで、土曜日のうちに掃除・洗濯といった家事雑事に加えて、簿記の勉強をそそくさと済ませ、東海道線をひた走る湘南新宿ラインに飛び乗ったのである。
学生時代を最後に湘南からすっかり足が遠のき、茅ケ崎にはもう何年も訪れていない。
ふと車内の中吊り広告に目をやると、辻堂のテラスモールが10周年を迎えたとある。
あそこができたのは、確か私が大学生の時分であったから、およそ十年ぶりということになる。

私が開高さんの存在を知ったのは、幼少の頃に偶然再生したビデオテープがきっかけだった。
当時の私は、ディズニーのアニメーション映画に加えて、父が録画した金曜ロードショーの「風の谷のナウシカ」をヘビーローテーションしていたのだ。
あるとき、いつものように「ナウシカ」のテープを再生したところ、巻き戻しがされておらず、続けて録画されていたドキュメンタリー映像が流れたことがあった。
それが、開高健の「モンゴル大紀行」だったのだ。
開高さんは私が物心つく前に亡くなられていたので、そのときは「丸顔に眼鏡をかけたおじさんが草原を流れる河に立ちこんで釣りをしている」程度の印象だったことを憶えている。
それから時は流れ、大人になって釣りをおぼえた現在、私は彼の著書を読み漁るようになった。
記念館では、二人して「水銀粒のように」世界を転げまわったという、ベトナム戦記以来の盟友カメラマン・秋元啓一に関する展示会が、先月から開催されている。
偶然にも、私の直後にやってきた来館者が朝日新聞出版の関係者であったようで、記念館職員との興味深い会話も漏れ聞くことができた。
「哲学者の小径」と名づけられた周回路に囲まれた庭から眺める書斎には、著書のなかで釣り上げた魚の剥製や往年の釣具が飾られ、将来自分の書斎を造りたいと秘めやかに願う私にとっては、堪らなく魅力的な空間である。
開高健は釣り好きの作家としても知られ、数々の著書を残しているが、秋元啓一と世界を釣り歩いた『フィッシュオン』のなかに、私にとって印象的な逸話があった。
「バンコックで本物の殿下に出会い、思いがけず、お邸にひきとられ、たいへんな厚遇をうけること」
この章で、私が一番好きな(食べるほうで)魚であるマナガツオが登場するのだ。
マナガツオはいくつかの古い文献にも記されており、そのなかでも
「マナガツオのマナとは、その身の美味なるを称していうなり」
「西海に鮭なく、東海に真魚鰹なし」
と謳われるなど、古来から人々がこの魚の美味を愛していたことが窺えるであろう。

『フィッシュオン』では、ボートから釣りをしつつ竿をせわしなく操りながら、開高さんが当時はまだ珍しかったキャッチアンドリリースの精神について語る場面にて、このマナガツオを釣ったときの様子に触れられている。
私は本書を耽読しながら、「ふぅん、東南アジアにもマナガツオがいるのか。ひょっとすると、シナマナガツオかな」などと想像していた。
文中で開高さんが思わずはしたない声をあげながら、
「マナガツオだ。マナガツオが釣れた。マナガツオだ。」
「これはうまい。味噌漬けにするとこたえられないぞ。」
「バンコックの日本料理屋にたのもう。これだけはもらって帰ろう。すげえ。」
などと大はしゃぎをしている情景を読み、その臨場感に魅せられた。
それと同時に、「うんうん。そうなんだよなあ」と大きく共感もしたものだった。
そのまま数ページを読み進めていくと、その時に釣れたと思われる魚が海面で銀鱗を輝かせている写真が、見開きで載せられているのが目に留まる。

しかし、ページを眺めてふと感じたのは、えも言えぬ違和感。
おそらく、この魚はマナガツオではなかったのだろう。
丸っこい形態のマナガツオに比して、頭部が妙に角張っているようだし、背鰭が著しく長く、まるで糸を引いているような魚の姿がそこにはあった。
どうやら、イトヒキアジかウマズラアジの類のようだ。
当時は開高さんも釣りを始めてから経験が浅かったと思われ、情報が瞬時に拡散される現代とは異なり、外国産魚類の分類に関する情報も今ほどは入ってきていなかったはずなので、形態が似ている外国産の魚を間違えてしまったのはいたしかたない面もあったのではないかと思う。
しかも、釣り上げた直後にあれだけ喜んでいる描写が書かれていたにもかかわらず、本書でこの“マナガツオモドキ”についての記述は、その後一切出てこなかった。
「食べてみたら不味かったから、たぶん違う魚だった」という後日談すらなかったので、その味は推して知るべしといったところだろうか。
おそらく持ち帰って食べたのだろうが、期待していたような味ではなかったので、開高さんはきっとがっかりして書く気も失ってしまったのではないかと、私は勝手に想像している。

それにしても、それまで釣った魚を逃がしてやることについて、生類憐みの放生哲学を語っていたにもかかわらず、マナガツオ(と間違えた魚)が海面に姿を現したら、途端に態度を変えてキープしてしまった開高さんには思わず笑わされてしまった。
いかにも釣師らしいエピソードであるし、この魚が文豪も思わず態度を変えた究極の美味だということは、間違いないといえるだろう。
そして、一般的に世間ではあまり認知されていないマナガツオという魚が旨いということを知っていたのは、やはり流石といったところでもある。
これは、マナガツオが関西地方で多く消費されていることから、氏が大阪出身であったことも影響していたのかもしれない。

ちょうど今夏、マナガツオの刺身と味噌幽庵漬けに舌鼓を打ったばかりだったので、唐突にこの開高さんとマナガツオの逸話を思い出し、心の中で思わず叫んでしまった。
「開高さん、それマナガツオちゃう!イトヒキアジや!」
しかし、数十年の時を経ては偉大なる故人に届くはずもなく、ベトナム戦記の二人の如く館内でしぶとく生き残っていた季節外れの蚊の猛攻に遭い、私はただ閉口するしかなかった。