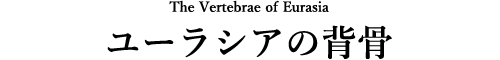大学時代には研究室でのフィールドワークの一環として、近隣を流れる二級河川の魚類調査に勤しんでいたことがある。
ウェーダーを履いてタモ網で魚を捕るのだが、その仕草から俗に言う「ガサガサ」と称されるものだ。
あるときそんな趣味が高じて、先輩や同期達と連れ立って放課後に多摩川の中流域にある支流へオヤニラミという魚を捕りに行った。
オヤニラミはスズキ目ケツギョ科に分類される小型の淡水魚で、鰓蓋にある美しい青色の眼状紋が特徴的だ。
その外見や人によく慣れる性質から、愛好家には鑑賞用としての人気も博する。
当時訪れた多摩川の支流でも、このオヤニラミをはじめムギツク・アカザ・ギバチ・タモロコなどたくさんの魚が姿を見せてくれた。
しかしだ。
そのほとんどが本来は多摩川にはいないはずの外来種だったのである。
オヤニラミの場合も本来の自然分布域は中国地方や四国といった西日本であり、もともと東日本には生息していなかったものなのだ。
魚類の外来種問題は近年の自然保護意識から認知度が高まって久しく、特定外来生物の指定など対策がなされてきたが、まだまだ世間で一般的なのはオオクチバスやブルーギルといった外国産のものだろう。
これに対して日本の在来魚類には違いないのであるが、人為的に分布域の外へ広がってしまった種は地味ながらもなかなかに厄介な存在で、国内外来種や移入種と呼ばれている。

淡水魚はその生息環境の特性から定着性が強いものが多く、止水域に外来種が侵入した場合では特に在来生態系への影響が大きい。
我が国の淡水域の多くは国内・国外問わず多くの外来生物によって、在来生態系が大きな被害を受けているといって良いだろう。
特に酷かった印象があるのが水生昆虫の調査で訪れた南西諸島で、その中でも沖縄本島の淡水域は壊滅的であり修復は不可能ではないかと思った。
また、愛知県のある遊水池でのかいぼり(池の水をすべて抜いて魚を獲ること)では、純粋な在来種はメダカ一匹のみで、他は数種類の国内移入種と四万匹ものブルーギルで占められていたこともあった。

東京屈指の大河川である多摩川もこの例に漏れず、数多くの外来魚をその懐に抱えている。
一説によるとその種数はなんと二〇〇種を超えるという。
オヤニラミどころかグッピーやエンゼルフィッシュにアロワナ、極めつけはアリゲーターガーまで確認されるようになり、誰が呼んだのかいつしかそんな現状を揶揄して「タマゾン川」と称されるようになってしまった。
当時の僕たちも「秘境タマゾン川!」などと言って、数多くのちょっと珍しい魚類が捕れるのを楽しんでいたのだと思う。
十年ほど前でさえそんな惨状であったのだから、現在ではその種数もさらに増えたかもしれない。
生まれ故郷が多岐にわたる彼らが棲みつくようになった経緯は推測の域を出ないが、多くは遊漁目的や飼育できなくなったものが身勝手に自然へ放されたのがきっかけだろう。

もともとその場所にいなかった生き物なのだから、本来なら駆除して環境から取り除くのが望ましいはずだ。
実際、僕自身も希少淡水魚の保護増殖を研究する傍ら、先述の毎年数万匹にのぼるブルーギルの駆除に関わった経験がある。
しかし、駆除とはすなわち外来種を殺すことに他ならないため、生き物好きとしては胸が痛まないはずがない。
これは、外来種問題に取り組む多くの人に共通する思いだと僕は信じている。
誰だって、好き好んで生き物を殺したいとは思わないのだから。
それに故郷を遠く離れた場所へ連れてこられても、立派に生き抜いている生き様は羨ましくあるほどだ。
だが、僅か数十年のうちに一度外来種に置き換わった生態系を復元するのに、いったいどれだけの年月を要するのか。
そもそも元に戻すことが可能なのか検討もつかないし、おそらく完全に元通りという訳にはいかないのだろう。

一方で生物資源の有効活用という面では、既に定着している外来魚を一様に無条件で駆除するべきとは言い難いのではないか。
トラウトフィッシングをする人なら、すぐに思い当たる節があるはずだ。
我々がその果敢な跳躍や強烈な引きに魅力を感じているニジマスやブラウントラウトも、歴とした外来種なのである。
あくまでも個人的な見解ではあるが、在来種の駆逐が軽微であり、人による管理が行き届いた釣り場や陸封された湖では、積極的な放流をせず彼らの自然繁殖に任せることを条件に、共存を図ってゆくことも考えられるのではないかと思う。
外来魚の問題は非常に根深い。
もしかすると、ニジマスもオオクチバスのように目の敵にされる時がくるかもしれない。
しかし人間の都合で遠く離れた土地に連れてこられて、挙句の果てに駆除されるのでは魚にとっては堪ったものじゃないだろう。
釣り人諸氏のお考えは如何であろうか。
「生き物に罪はない。けど彼らは本来ここにいてはいけない生き物なんだ。」
懐かしい恩師の言葉が胸に浮かんだが、しかし車窓から眺める払暁の青白き多摩川に吹く風が、慧解を与えてくれることはなかった。