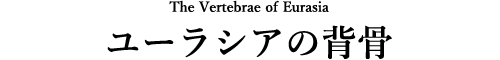北海道でルアーフィッシングをしていると、しばしば招かれざる獲物と遭遇することがある。
銀鱗を輝かせながら、特徴的な尖った吻の口でサッとルアーを掻っ攫っていき、適当にリリースされても颯爽と湖に帰って行く。
如何にも外道然とした魚。それがウグイである。
今から数年前。
まだイトウのルアーフィッシングを始めてから、ようやくまともに魚が釣れるようになったばかりのことだ。
しかし、その頃の僕には、とにかくウグイばかりが良く釣れた。
どのくらいかというと、他の人がイトウを一匹釣る間に、僕はウグイを五匹は釣っていたと思う。
一日中同じポイントで一緒にやっているのに、こんなにも差が出るものなのだろうか。
無論、イトウはなかなか釣れない。
さらに数日間の釣行全体で見れば、皆はせいぜい二、三匹なのにも関わらず、僕の釣果はゆうに二桁を超えるウグイで大半が占められていた始末である。
「朱鞠内のウグイキラー」
文字通りまさしくこれは、あの頃の僕を形容するに相応しい称号だ。
当時は何故こんなにもウグイばかり釣れるのか、不思議で仕方がなかったものだ。
単純に、ただ運が悪いだけなのかも知れないと思っていたくらいだった。

あるとき、もう何匹目だか数えるのも面倒になったウグイを、ランディングネットに収めた。
如何にもイトウが身を潜めていそうな倒木を攻めたのだが、その陰から勢いよく飛び出してルアーに喰ってきたのが、こいつだったのだ。
ウグイもある程度の大きさになればそれなりのパワーで抵抗してくるため、一瞬だけイトウの幼魚でも掛かったのかと期待してしまう。
小さくても、本命のイトウなら少しは気も紛れるというものだ。
しかし、次の瞬間には寄せてきた魚影を視認して、期待が失望に変わる。
さらにこのウグイという魚、ルアーにアタックしてくる時の俊敏さの割には、非常に間抜けな一面を見せることがある。
さっさと放してしまおうと、こちらはネットの網口を広げているのに待っているのに、わざわざ網袋の奥に向かって突っ込み続けたり、逆にネットの開口部付近でいつまでも出ていかずに、ゆらゆらと佇んでいたりするのだ。
仕舞にはこちらが痺れを切らし、ネットをひっくり返してバシャッと雑にリリースをすることになるのだが、何食わぬ顔でそそくさと泳ぎ去って行くところがまた甚だ憎々しい。
ところが、僕にウグイばかりが釣れていたのには、歴然とした理由があったのである。
しばらく後に、近くで同じように釣りをしていたFさんに指摘されて、ようやく気が付いた。
それは、ミノーをデッドスローでリトリーブしていたからだった。
冷静に観察してみれば、イトウ釣りの名手であるMさんのリトリーブスピードと比較して、僕のそれは半分くらいの速さだ。
おそらく、ふらふらと失速寸前のように泳ぐミノーのアクションが、ウグイの眼からは特別に魅力的であり、他の魚が喰いつく前に、その動きに対して反応性が高いウグイが釣れてしまっていたのだろう。

そういえば、一度キャストミスをして、ルアーが水面から飛び出すほど全力で回収していたら、途中でアメマスが釣れてしまったことがあったから、あれとは逆のパターンなのかもしれない。
いつだって、魚はきちんと自分の釣り方に解答を示してくれていた訳である。
その頃を境として、僕にもイトウやアメマス、サクラマスが釣れる確率が格段に増し、相対して徐々にウグイの顔を見る機会は少なくなっていった。
ちなみに、以前は阿寒湖にも僕と同じような、デッドスローリトリーブ使いのウグイキラーが居たらしい。
地元在住のその人、MOさんは阿寒湖で初めて会ったFさんのあまりに大きなルアーに驚いて、新品の小さなルアーをいくつかプレゼントしてくれたそうだ。
以降、Fさんを盟主とした輪が広がり続け、最後に加わった僕も、いつしか一緒に釣りをするようになった。

彼は去年78センチのモンスターレインボーを釣り上げ、今年の春は大島で釣りをするMさんの前に、サンダルとスウェット姿で現れた。
そして、全く釣れないMさんを横目に、サクラマスを一匹だけ釣って颯爽と帰って行ったそうなのだが、二日間続けて手作りの温かいお弁当を持ってきてくれたというのだ。
まあ、それが彼の本職なのだから当然とはいえ、そのお弁当はとても美味しかったそうで、奇しくもサクラマスを横取りされた形となるMさんの命名で、「元・阿寒湖のウグイキラー」は、その日から「優しい厄病神」へと変貌を遂げたのだった。
お世話になっているMOさんには失礼を承知で書くが、これって本質的には北海道のウグイと同じ役柄じゃないだろうか。
「優しい厄病神」
ウグイに何か称号を与えるならば、これほど相応しいものはないかもしれない。
お目当ての魚が釣れない無機質な時間の中で、時折サッと顔を覗かせて、釣り人の気を紛らわせてくれる。
きっと、何も釣れないよりは遥かにマシな訳なのだから。
今でもウグイを釣るたびに、僕もウグイキラーだった頃のことを思い出す。